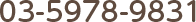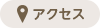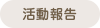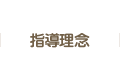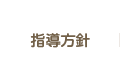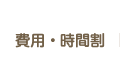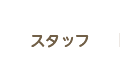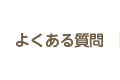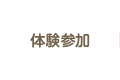カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年4月 (4)
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (3)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (3)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (3)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (3)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (3)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (3)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (4)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (3)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (3)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (5)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (3)
- 2018年5月 (3)
最近のエントリー
HOME > 活動報告 > アーカイブ > 立体造形 > 10ページ目
活動報告 立体造形 10ページ目
円柱紙管のオブジェ
造形 個人制作 2019年2月2週目
1週目に使った紙筒で、円柱の止まる特性を活かしオブジェを作りました。
同じ素材が、それぞれの工夫で、活かすことのできる面白さを体感しました。
幼児・小学生クラスはまず様々な長さの紙管を組み合わせて色を塗った作品を何点か見せました。子どもたちは感じたイメージを伝え合い、触りながら確かめていました。そのうちに材料は先週電車を動かす為に使った紙管だと気がつく子がいました。「これを今日は違う形に変身させてみよう」と伝えて始めました。
まず色んな長さの紙管を並べたり積んだりしてどんな形にしようか試行錯誤していました。その中で紙管を取り替えたり板を繋げて大きくしたり、子どもたちは自分のイメージに近づける為に様々な工夫をしていました。イメージが広がり、部品が足りない小学生は、長い紙管を自分で電動糸ノコで切って使いました。振動する紙管をしっかり抑えてみんな真剣な表情で切っていました。形が決まるとボンドで貼り合わせました。板に貼り付けたり、紐でつなげたりする子もいました。そして好きな色を塗りました。今回はもともとみんなで色をつけた素材を使用しているので、それを活かせるように先週使った薄めた絵の具を重ねていくか、白色の絵の具で全部真っ白にしてから新しく色を塗るかそれぞれ選んで塗りました。終わりの頃にはみんなで遊んだ紙管は子どもたちの手によってすっかり新しく、いろいろな形に変わっていました。
親子クラスは最初にいろんな長さの紙管を見せて、積んだり転がしたり思い思いの方法で遊びました。その後板にボンドで貼り付けて、先週使った絵の具を重ねて塗りました。紙管で遊ぶのも作るのもどちらも集中してたっぷりと触れ合っているように感じました。


2019年2月18日 10:00
コマ作り
造形 個人制作 2019年1月3週目
形や模様や色に、動きを加えることで、見え方が変わってきます。その様子を、自分で作ったもので遊びながら体感できるよう、コマを作りました。
始めに親子・幼児クラスでは「まわる」をテーマにした絵本を読みました。幼児クラスでは更に身の回りにある「まわる」ものは何だろう?と考えてみると、「換気扇」「フラフープ」「ケーキを作る時にくるくる混ぜるよ」など色々な意見が出てきました。その後いろんな形のコマの見本を見せると、先週の絵画の活動のモチーフで出てきたのを思い出し、「絵を描くときにあったね!」「コマも確かにまわる!」などと、とても嬉しそうでした。四角・三角のような形・フニャフニャやギザギザな形など、どんな形でも回してみると円の形が見えてきます。それを発見した子どもたちはとても驚いた様子でしたが、同時にどんな形でも回せるのだということがわかり、安心して自分の描きたい形へと、発想を広げることが出来ていたようでした。
小学生クラスでは更に色の塗り方の違うコマも回してみせました。ランダムに色を塗ったコマと、定規を使って色面分割したコマでは、回したときに色の見え方が違います。
いろいろな見本を見た後に自分の作りたい形を想像し、色の塗り方や飾りのつけ方を決めてから、切り出す形を決めて制作に臨みました。
まず四角いベニヤ板に作りたい形を鉛筆で描き、電動ノコギリで切り出していきました。少し大きい音のする機械にちょっとドキドキしている様子の子もいましたが、一緒に少しずつ切っていくと、どの子も上手に自分の好きな形が作れていました。切ったベニヤ板はヤスリがけをしてから飾りの小さいベニヤ木端を貼り付け、白ペンキで下塗りをしてから色を着けていきました。具体的な形を作りたい子、好きな色を塗りたい子など、それぞれのやりたい事に焦点を当て、制作を楽しむことが出来ていたようでした。
最後に裏側に半球の木端をつけて出来たコマを回してみると、自分の作ったもので遊べる喜びを感じたようで、どの子も嬉しそうな表情だったのが印象的な活動となりました。


2019年1月28日 10:00
積み木あそび
造形 集団制作 2019年1月1週目
単純な形の組み合わせから複雑なものができることや、1つの空間で、それぞれの作品が調和する様子から、つながりあってできる楽しさを体感しました。
親子・幼児クラスはまず、「おててマン」と「おててかいじゅう」が積み木の世界に出てくる絵本を読みました。「みんなはおててマン?おててかいじゅう?」と声掛けすると、「おててマンになる!」「先生はおててかいじゅうにならないでね?」などと色々な声があがり、楽しい雰囲気の中で活動が始まりました。
親子クラスでは予め部屋の中に角棒を使って川を作り、その周りの好きな場所に積み木を積んでいきました。一つずつゆっくり積み木を積んだり、時には壊してみたりと、積み木という素材と純粋に向き合うことを楽しみながら活動が進みました。最後に角棒の川の中にビーズのお水を流し、体を動かして遊びました。
幼児クラスではテーマを特に決めず、好きなものを作りました。子どもたちの発想の手助けになるよう、部屋の中に土台となる板を設定し、そこに作りたいものを考えながら、それぞれ自由に積んでいきました。一人で作ったり、何人かで一緒に作ったりと、子どもたちの想像の世界がどんどん広がっていきました。
小学生クラスではそれぞれが自由に作りながら、最後には1つの世界を作り上げることが出来た達成感を心地よく感じられるように、まず始めにみんなで話し合い、自分たちで1つのテーマを決めていきました。色々な意見の中から 街・建物・家などのテーマの下で取り組んだクラスが多かったです。何が作りたいかテーマを意識して考え、そこから発想をどんどん膨らませて自分の世界を作り上げていきました。
どのクラスでも、それぞれが作った作品が最後には一つの調和した世界となり、子どもたちもみんなで作る楽しさ、大きな達成感を感じられている様子でした。


2019年1月14日 10:00
ケーキと積み木でクリスマス
料理 個人制作 集団表現 2018年12月3週目
形のテーマ―と季節に合わせ、米粉を使って、四角いケーキを作りました。
積み木とお菓子の作品を囲み、みんなでクリスマスの雰囲気を味わいました。
この季節といえばクリスマス。毎年12月最後の活動は、色々と趣向を変えながら、そんな雰囲気をみんなで楽しむ活動を行っています。以前からいるこどもたちは、今年は何?と楽しみしてくれている活動です。今年は米粉を使ってケーキを焼いて、積み木を使って思いに作り、そのイメージを表現してみました。
今日は今年最後の活動なので、お菓子を作って、あとはお愉しみ…と伝えると何だろう?どんなお菓子?と想像を膨らせていました。いろいろな材料を一つずつ味見しながら混ぜ合わせ、そのあと粉に入れて混ぜました。パンを今年作ったときと材料が似ているのですがその時は小麦粉、今回の粉は米粉です。似ているけど違う、感触や味に気づいた子どもたちは、どんなふうになるのかとさらに想像を膨らませていました。
そのあとレンジで作ったリンゴのジャムをメインに、好きなドライフルーツやナッツを混ぜて四角い型に入れました。大きなボールから小さな型に流し込むのは難しいそうでしたが上手にこぼさず入れていました。
お菓子をオーブンに入れ焼いている間、積み木でツリーやクリスマスからイメージするものを作りました。
普段遊んでいるものがテーマを作ることで、新しい発想がひろがり、つながっていきます。それぞれが工夫をこらして自由に制作しながら、あっという間に壁一面に素敵なかざりができていきました。
最後にみんなで積木のツリーを囲み、部屋のイルミネーションを点灯させ、おやつを頂きました。ライトアップされると思わず歓声があがりました。積木もとても綺麗で、いつもとは違う特別な雰囲気の中、自分たちで作ったケーキを食べながら、みんなでアトリエならではのクリスマス楽しみました。


2018年12月24日 10:00
大きな円錐のオブジェ/円錐のオブジェ
親子幼児クラス 造形 集団制作/小学生クラス 造形 個人制作 2018年12月2週目
前回、どこから見ても三角形でできている三角錐を作ったつながりから、今回は上から見ると円、横から見ると三角形の円錐をモチーフに制作しました。
親子幼児クラスは最初に先週の三角の制作を振り返り、「今週は三角の仲間で遊ぼう」と円錐の形の積み木を1つ見せました。そこに大きな円錐も出てきて、子どもたちは、初めはびっくりしながらも体いっぱい遊びました。そのあと1枚の紙が巻かれた同じ円錐を出して、その紙を床に敷いて絵の具を垂らしてみんなで筆で思いっきり塗ったくりしました。中には手や足や身体全体を使って塗る子もいました。
破けそうなほど色を重ねた紙を円錐に巻き戻して遠くから見ると、子どもたちから「クリスマスツリーみたい!」という声が聞こえてきました。そこで絵の具を付けたポンポンで色をつけたり、毛糸を巻いたり、綿を貼ったりして飾り付けをすると、温かい雰囲気の素敵で巨大なクリスマスツリーが出来上がりました。
小学生クラスは幼児クラスで作ったクリスマスツリーを見ながら、「一枚の紙でどうやって円錐を作るでしょう?」と問いかけ、それぞれにまず挑戦してみました。
習うのではなく自分で作ってみることで、その形状を捉えていきます。巻いたり三角を作ったり、子どもたちは一生懸命考え、試行錯誤しながら作っていました。その後もともと作っておいた円錐を開いて半円の状態を見せると、子どもたちは円錐への理解を深めている様子でした。作品は改めて半円の厚紙で好きな角度の円錐を作って、そこ全体に粘土を貼って好きな形を作ってから好きな色を塗って作りました。円錐からイメージしたものを自由に作る活動でしたが、やはりツリーを作る子が多く、それぞれ個性的なツリーを作っていました。他にも帽子や生き物、オブジェなど発想が楽しいものなど、どれも同じ形からできたのは思えないほどユニークな作品が出来上がりました。


2018年12月17日 10:00
ストローの変身オブジェ
点線面から三角 造形 個人制作 2018年11月1週目
単純な直線を、いくつか組み合わせることにより、多様は形を表現できます。
身近な素材を使い、それぞれの感性で変化させ、いろいろな作品ができました。
今回はまず予め作っておいた作品見本を子どもたちに見せて、素材は何でできているのか、どうやって作ったのかをみんなで考えるところから始めました。
素材のストローは普段の生活に馴染みのある物なので、すぐにわかったようですが、それがどのようにつながっているかはすぐにはわかりにくく、関心をしめしたようで、作品をよく触ったり覗いたりしながら、どの子も一生懸命考えていました。
イメージをつかんだところでストローにビニール用の絵の具で色を着けた後、ストローを好きな長さに切り、針金に通していきました。
親子・幼児クラスは最初に電車が連結していく絵本を読んだので、お話にでてきた「れんけつがっちゃん!」のリズムに合わせ、ストローをつなげていきました。
塗ったり、針金にとおしたりする細かい工程でしたが、手先を器用に使い、楽しみながら行っていました。
小学生クラスでは少し硬めの針金と、細くて柔らかい針金の2種類を用意し、更にストローの色(白か透明)や絵の具の種類(ビニール用絵の具かアクリル絵の具)も、好きな組み合わせを選択して作品づくりに臨みました。
針金の硬さが違うだけでも出来上がる作品の印象が全く違いますし、更にストローを同じ長さに揃えて切るか、バラバラの長さに切るかでも全然違った作品が出来上がります。
それぞれ自分の作りたい作品のイメージに合った手順で制作を進め、最後にはそれぞれ違った個性的な作品が揃いました。
作品は針金の伸び縮みを活かして遊んだり、好きな形に折り曲げて置いて飾ったり、上からテグスなどで吊るしたりして飾ってもとても素敵です。いろいろと工夫して楽しんでください。


2018年11月11日 10:00
アルミホイルレリーフ/銅板レリーフ
親子幼児クラス 造形 個人制作/小学生クラス 造形 個人制作 2018年10月2週目
単純な線を動かし、組み合わせながら、いろいろな模様を描いてみました。
アルミホイルをかぶせてメタリック素材の風合いを活かした作品を作りました。
最初にタコ糸で見立て遊びを楽しんだ後、スチレンペーパーの台紙にタコ糸やロープ・輪ゴムなどの線状の物を好きなように構成して貼り付けました。そこにアルミホイルをかぶせてフタをしてしまいました。でも上から布で優しくおさえていくと、線の模様の部分が浮き上がってきます。模様が見えなくなって心配そうな子ども達でしたが、模様が浮き上がる様子を見ると自然と歓声が上がっていました。その後には金属に色を着ける時に使う下地剤とインクを混ぜた特別絵の具でツルツルした面への色塗りを楽しみました。
紙や木材に色を塗った作品とは違う、不思議な風合いの美しい作品がたくさん出来ました。
銅板に好きな形の素材を置いてたたきつけ、模様を組み合わせて描きました。
それぞれの工程を素材の性質を活かし、実験感覚で楽しみながら制作しました。
制作前の銅板を見せたあと、その銅板で作った作品を見せて、どうやって作ったのかみんなで話し合ってから制作しました。
まず銅板に様々な形の素材を打ち付けて跡をつけ、その後硫黄の匂いがする入浴剤入りの水にその銅板を入れて腐食させました。段々と黒くなる様子をみんな興味深そうに観察していました。
黒くなった銅板を最後に紙ヤスリなどで磨きました。磨かれた部分から元の色が出てきて模様が浮き出てきます。中には職人のような顔つきで磨いている子もいました。
子どもたちは使い慣れない素材にそれぞれの方法で向き合って、最後はとてもかっこ良くユニークな形に仕上がっていました。


2018年10月22日 10:00
積み木あそび
親子幼児クラス 造形 個人制作 2018年9月3週目
大きさや色の関係性のある細長いカラフルな積み木で遊びました。1つの台の上にみんなで作ることで自然とつながり、調和した大きな作品ができました。
始めに先週同様、平面に積み木を組み合わせていろんな形を作りながら、見立てて遊びました。前回と違い直線だけで具体的なものを作るのは難しいのですが、描いたのもがイメージできる形をうまく表現していました。次にみんなで1枚の板の上に積み木を積んで遊びました。それぞれ好きなように積んでいるうちに、横へ縦へと大きくなっていくのを見て、自然とつなげたくなったようです。何度も倒れたり、直したりを根気よく繰り返しながらみんなで作った大きな作品を眺め、どの子も満足そうな表情をしてました。


2018年10月 1日 10:00
木っ端のマリオネット
小学生クラス 造形 個人制作 2018年9月2・3週目
いろいろな道具を使って活動しました。完成までの複雑な工程を、じっくりと試行錯誤しながら取組めるよう、2週続けて1つの制作に取り組みました。
まず初めにあらかじめ作っておいたマリオネットを「こんにちは!」と取り出して見せました。みんなで遊んでみた後に様々な形の木っ端を見せて、「これで動かして遊べる好きな形のマリオネットを作ってみよう」と伝えると、子どもたちはわくわくした表情で取り掛かりました。人間や動物、ロボット、乗り物、建物などそれぞれが自由にイメージを膨らませていました。
作りたい形が決まったら、可動部分に手動ドリルで穴を空けてヒートンをねじ込みました。入らない時はキリで下穴を空けたり、ねじ込む時はペンチを使ったり、子どもたちは普段あまり使うことのない道具を工夫しながら使いこなし、意欲的に取り組んでいました。全部取り付けられたら合体させて、さらにマリオネットのひもを付ける為のヒートンもつけました。だいたいの子がこの辺りで1週目の活動を終えました。
2週目が始まる際は早く続きをやりたがる子が多く、活動時間の前でも来た子からどんどん始めました。
形が出来たら色を塗りました。いろんな色で塗りたい子は白いペンキで下塗りしてから好きな色で塗りました。木の色合いが気に入った子はニスを塗りました。最後に棒を選び、紐で作品と棒を結んで繋げました。紐を結ぶのが初めての子も、一生懸命取り組んでいました。
紐がついて完成した作品をあやつり、手足が動く様子を見ると喜びが大きく、楽しそうに歩かせる練習をしたり、いつまでも作品で遊んでいたりとその子にとってとても愛着のある作品になっている様子でした。


2018年10月 1日 10:00
へんてこどうぶつ?!
親子幼児クラス 造形 個人制作 2018年9月2週目
具体的なイメージにとらわれずに発想が広がるよう、へんてこへんてこ…と、不定形ないろんな形を組み合わせて、個性豊かないろんな作品が誕生しました。
最初に読んだ絵本から得たイメージをもとに、ベニヤ板を組み合わせていろいろなものを表現しました。大小様々な形にカットしたベニヤは、少し組み合わせを変えるだけでも、全く違った形が出来上がります。子どもたちは色々と並べてみながら、自分の好きな組み合わせを探していました。
親子クラスはベニヤを貼り合わせてから色塗りをし、幼児クラスはベニヤをバラバラのまま色を塗ってから貼り合わせました。最後におはじきで目などを表現すると、自分だけのへんてこどうぶつの完成です。それぞれとても個性的で、心なしか作った子どもたちに少し似ているような、可愛らしい作品がたくさん誕生しました。


2018年9月24日 10:00
<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|次のページへ>>