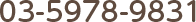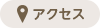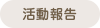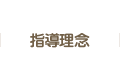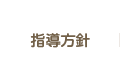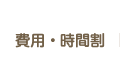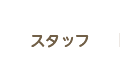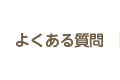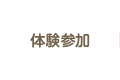カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年3月 (4)
- 2025年2月 (3)
- 2025年1月 (4)
- 2024年12月 (4)
- 2024年11月 (4)
- 2024年10月 (4)
- 2024年9月 (3)
- 2024年8月 (3)
- 2024年7月 (3)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (3)
- 2024年4月 (3)
- 2024年3月 (3)
- 2024年2月 (3)
- 2024年1月 (4)
- 2023年12月 (3)
- 2023年11月 (3)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (3)
- 2023年8月 (3)
- 2023年7月 (3)
- 2023年6月 (3)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (3)
- 2023年2月 (3)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (3)
- 2022年11月 (3)
- 2022年10月 (3)
- 2022年9月 (3)
- 2022年1月 (3)
- 2021年12月 (3)
- 2021年11月 (3)
- 2021年10月 (3)
- 2021年9月 (3)
- 2021年8月 (2)
- 2021年7月 (3)
- 2021年6月 (3)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (2)
- 2020年12月 (3)
- 2020年11月 (3)
- 2020年8月 (4)
- 2020年7月 (4)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (3)
- 2019年11月 (4)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (6)
- 2019年7月 (3)
- 2019年6月 (3)
- 2019年5月 (3)
- 2019年4月 (3)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (3)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (3)
- 2018年11月 (3)
- 2018年10月 (5)
- 2018年9月 (5)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (3)
- 2018年5月 (3)
最近のエントリー
活動報告
コラージュ版画
造形 集団制作 2019年9月1週目
みんなで1枚の紙に、いろいろな素材を貼り合わせて版画をしました。個々の表現、いろんな形が1つの面でつながり、ダイナミックな作品ができました。
最初にへびくんが出てくる絵本を読んだ後にアトリエに現れたのは、へびくんのような細長いテーブルです。その上にへびに見立てた画用紙を敷いて、色々なご飯(素材)を貼って食べさせました。絵本にでてくるへびくんがなんでも飲み込んでしまう食いしん坊だったので、子ども達もそれをイメージしながら「はい、おにぎりだよ!」「これはおせんべいだからね」などと言いながら楽しんでご飯をあげていました。
小学生は素材を一面まんべんなく貼っていく子もいれば、自分の作りたい形を頑張って作っている子もいました。今回は形の組み合わせで好きな模様を描いてほしいと思い、はじめから素材を自分で好きな形に切るのではなく、こちらが用意した様々な形の素材を使ってもらったのですが、その中から自分のイメージに合うものを探し、並べ方など工夫しながら見事に具体的なものを表現できた子も見られました。
画用紙に素材をたくさん貼った後には、へびくんに版画インクのジュースをあげ、画用紙と同じ長さの障子紙をかぶせて版画を刷りました。
画用紙に素材をたくさん貼った後には、へびくんに版画インクのジュースをあげ、画用紙と同じ長さの障子紙をかぶせて版画を刷りました。
今回は色々な形が集まって模様ができあがることを感じてほしかったので、模様が統一されるように1色刷りを2回行いました。みんなで相談してインクの色を選び、ローラーで全体に塗り、障子紙をかぶせてバレンでこすると、だんだんと模様が浮かび上がってきます。その様子に子どもたちは大興奮しながら、最後に障子紙に写った模様を見せると自然と歓声が沸き上がっていました。
出来上がった作品は天井から吊るして飾るとより迫力のあるものとなりました。それぞれが好きなように素材を貼り、表現したものが合わさって、見事に調和した1つの世界に仕上がっていました。


カテゴリ:
2018年9月17日 10:00
同じカテゴリの記事
紅白まんじゅう
全クラス 料理 個人制作 2025年2月3週目
円柱の素材から球を作る経験を、おまんじゅうを作ることで体感しました。自分で作ったお菓子を囲み、最後はみんなで、美味しく楽しく過ごしました。
進級・進学の時期にあわせ、お祝いの気持ちを込めて、紅白のおまんじゅうを作りました。形のテーマに基づく材料は、円柱のさつまいもです。蒸し器にいれて蒸かしている間、おまんじゅうの生地を作ります。生地を、打ち粉とまぶして練りながら、色をつけたり練り込んだり。ベタベタする柔らかい生地をまとめるのは大人でも加減の難しい工程でした。子どもたちは伝えるコツを良く聞きながら、容器や手にくっついて食べる分がなくならないよう一生懸命、気をつけながら作っていました。
蒸し上がったさつまいもを練ってあんにするため、熱々の状態でむきました。あまりしてない経験に、「熱いよ。無理だ!」などといいながらも、頑張ってむいていました。最後にできた生地に作ったいもあん、用意しておいたあんこを丸め、生地を丸く広げて包み、蒸し器で蒸したら完成です。蓋をあけて大きくふくらんだおまんじゅうが登場すると思わず歓声があがりました。自分で作ったからでしょうか、甘いものが苦手なお子さんも、これは食べられると嬉しそうに食べていました。


2025年2月24日 10:00
円柱紙管線路の描画
全クラス 造形 集団制作 2025年2月2週目
円柱の転がる性質を活かして遊んで描きました。それぞれの色が円柱の動きで折り重なり、意図して作ることのできない模様の誕生を楽しみました。
始めに円柱の積み木で遊びました。形の特性を伝えなくても、子どもたちは遊びを通して感じたようです。同じ円柱の紙管を加えると、さらに特性を活かして高く積んだり、転がして的当てゲームをしたりと、どんどん遊びの幅を広げていました。
自由に遊んだ後は、細長い円柱紙管を線路にみたて、床に敷いた画用紙の上に並べていきました。電車がよく走るように絵の具のオイルを垂らし、電車に見立てた板を乗せれば準備完了『出発進行!』子どもたちをのせて板を押すと紙管の上をスーッと走っていきました。お客さんになったり電車を走らせたり、時には整備士になって電車がよく走るように枕木を調整したり、どのクラスもみんな電車の世界に浸りながらとても楽しそうに遊びに参加していました。気が付くと紙管の転がりによって絵の具がのばされ、手で描けないような、綺麗なグラデーション模様が描かれました。子どもたちは夢中であそびながらその美しさと、意図せず遊びの中で自然とできた作品との出会いに驚き、喜びを感じられている様子でした。


2025年2月17日 10:00
コマを作る
全クラス 造形 個人制作 2025年2月1週目
描いた形に、模様や色に動きを加えることで、見え方が変わってきます。
その様子を、自分で作ったもので遊びながら体感できるよう制作しました。
四角・三角のような形・フニャフニャやギザギザな形などいろんな形を回してみました。どんな形でも回してみると円の形が見えてきます。その様子やどんな形でも回せるのだということを感じた子どもたちは、自分の描きたい形へと、発想を広げることが出来ていたようでした。ランダムな色付けと分割彩色したコマでは、回したときに色の見え方が違います。小学生はそんな違いも回して感じ、塗り方や飾りのつけ方も想像し制作しました。
四角いベニヤ板から電動ノコギリで切り出し、好きな形を作りました。少し大きい音のする機械にちょっとドキドキしている様子の子もいましたが、だからこそそれぞれ真剣に取り組み、自分の好きな形が作れていました。具体的な形を作りたい子、好きな色を塗りたい子など、それぞれのやりたい事に焦点を当て、制作を楽しむことが出来ていたようでした。最後に出来たコマを回してみると、自分の作ったもので遊べる喜びを感じたようで、どの子も嬉しそうな表情だったのが印象的でした。


2025年2月10日 10:00
ランドセル・凧とコマ
幼児小学生クラス 絵画 2025年1月3週目
モチーフと向かいあい、見たまま、自分の感じたイメージを表現しました。
幼児、小学生はモチーフを見ながら絵を描きました。今回のモチーフは季節と四角い形を意識して、お正月らしい雰囲気の凧とコマと、もうすぐ新年度なのでランドセルを用意してみんなに紹介しました。
コマを触ったり回したり、モチーフを触れたり観察して、描きたいものを決めていきました。幼児はランドセルを間近で見たことのない子もいて、興味津々開けたり背負ったりしながら確かめていました。
まずは木炭で大まかな形を捉えてから絵の具で好きな色を塗りました。子どもたちは真剣な表情でモチーフと向き合いながら、それぞれが気に入った部分をこだわったり、モチーフから自分のイメージを広げたりしながら、一生懸命描いていました。終わりの頃にはアトリエに味わい深い作品が並んでいました。


2025年1月27日 10:00
四角のスタンプ描画
親子クラス 造形 個人制作 2025年1月3週目
いろいろな素材の四角柱を使って、遊んだり、描いたりして遊びました。
親子クラスは初めに絵本を読んでからボールの入った箱を出して遊びました。いつもならすぐに頃が足したり投げたりすることが多いのですが、蓋を開けてボールをとりだしたせいか、野菜やくだものに見立てて遊ぶ子が多かったです。一つのイメージにこだわらず、感じたままに広がっていく発想に感心しながら素材を加え、保護者の方と一緒に遊びを展開していきました。最後に遊んだ箱にインクをつけて、形を視覚で体感しました。箱以外にも発泡スチロール、木っ端など、用意したいろんな素材の四角から気に入ったものを見つけて何度もスタンプして、たくさんのいろんな四角が重なった素敵な作品が出来上がりました。


2025年1月27日 10:00